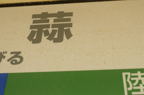【企画展】希望の一滴 〜被災地で見えたもの〜
サムネイルをクリックすると写真が大きくなります。
忘れもしない2011年3月11日金曜日。
三陸沖を震源とする、東北地方太平洋沖地震が発生。
そのあまりにも巨大な自然の猛威に、各地の被害も甚大で、東日本大震災と呼ばれる事になる。
被災の状況は、メディアの報道に譲るとして、自身の眼と脚で、現地を見て回る事にする。
失われたものがあれば新たに生まれたものもある。後退があれば前進もある。闇があれば灯りもある。
そこには、
圧倒的な被害の大きさの中に、微かな、それでいて力強い息吹があった。
あくまで近隣の市町村に比べてではあるが、人的被害が少なかった塩竈市。
それでも数mの津波が襲来し、岸壁は破壊され街中が浸水している。決して軽微とは言えないのである。
建物にしろ施設にしろ、真新しい物があると、複雑な気分だ。
本塩釜駅前には数々のモニュメント。切っても切れない、海と魚の街である。
仮設商店街は、訪れた2日前に閉鎖。移転先での本当の再開に向けて、撤収作業に精を出す。
マリンゲート塩釜からは、離島航路や松島巡りの遊覧船が元気に発着していた。
松島湾の根元に張り出した半島。三方が海に面していて、七つの浜で七ヶ浜。
松ヶ浜のすぐ南は仙台港。海鳥のコロニーの向こうを大型貨物船が横切る。
菖蒲田の浜は大規模工事中。延々と続く茶色い色彩に、干してある漁網の緑がキラリと光る。
花渕の浜にハマヒルガオ。人工物は壊れても野生の花は咲く。人工物を押し退けてでも力強く咲く。
吉田浜の高台にある、君ヶ岡公園の展望台からは、各方面の浜の遠望。
初めて被災地を訪れた時、仙台から仙石線と代行バスを乗り継いで、石巻へ向かった。
その車窓から、最初に状況を目の当たりにしたのが、東名〜野蒜地区だった。
とにかく息を飲んだ。全てが流されていた。陸地であるべき所が浸水して、大型バスが田んぼの畦道の様な道を走っていた。
仙石線の不通区間が、内陸寄りにルートを変えて復旧。最新のハイブリッド気動車に乗って訪れた。
5日前に移設再開したばかりの、ピカピカの野蒜駅が眩しかった。
大きく被災しながらも流失を免れた旧野蒜駅は、綺麗に改修され、コンビニと地域交流センターとして再利用されていた。
津波の時刻で止まっていた壁時計は、ちゃんと現時刻を刻んでいた。
桜咲く高台の日和山公園。沿岸部を一望できる。本来なら絶景である。
そこから見下ろした門脇地区。言葉を失うとはまさにこの事である。
瓦礫もおおかた片付けられて、素っ裸になっている。
しかしただの野原ではない。
信号や自動販売機には電気が通じ、往来を整理し、人々の喉を潤す。
津波に耐えて踏ん張った松の木の枝には、鳥が巣を作り、根本には松笠が落ちている。
何処の場所にも平等に、陽は昇り、そして沈む。
石巻市内であるが、合併前は旧雄勝町であったこと、中心市街地から離れていることから、別項目として扱う。
良質の石が採れる町で、硯の生産で全国的に有名。復原された東京駅丸の内駅舎の、スレート屋根に使われた事が話題になった。
屋上にバスが打ち上げられた公民館など、震災遺構と呼べるものは既に撤去されている。
海岸線すぐそばまで迫った山に、おそらく野生の素朴な桜の木。ちょうど満開。
前回訪れた時は、雨が本降りとなり早々に切り上げて逃げ帰ってしまった。
今回リベンジだ。旧総合支所を拠点に、各方面を歩いて巡る。
前回とは時期が違う。新緑が萌える。遠目に見て色合いが違うだろう。
水浜地区と小島地区。雄勝湾を挟んで対岸がすぐそこに見える。それだけ細長い入り江ということ。
鰻の寝床という言葉があるが、ここはウニやホタテの寝床である。
おそらく震源に一番近い町なのではなかろうか。人口に対する犠牲者の割合では、全国一だったはず。
かつての女川駅は、痕跡を探す事さえ難しい。
倒壊でなく横倒しになった3棟のビル。地面から引き抜かれた基礎の杭では、雀が休息。
地盤沈下した漁港の桟橋には、たくさんの漁船が係留され、何事も無かった様にウミネコが集う。
復興商店街が元気なのが嬉しい。
本当の復興はまだまだだと、誰もが口を揃える。
けれど、見かけの復興は着々と進んでいる。
海沿いの国道から、津波の爪痕の残る階段を、駆け上った高台にある地域医療センター。
遥か見上げた海抜10数mであるが、今ではそこが市街地のグラウンドレベルだ。
類を見ない大規模なかさ上げ工事のおかげで、周辺の山がみんな虎刈り。
3棟あった横倒しビルは、2棟が解体され、残った旧女川交番は、メモリアルパークとして保存・整備中。
震災から4年ぶりに、場所を移して再開した女川駅の、モダンな駅舎がランドマークとなっている。
さんさん商店街は、復興商店街のリーダー的存在。観光客の招致に力を入れているのがわかる。規模も大きくとても賑わっている。
その傍らにあるモアイ。門外不出のイースター島から震災を悼んで贈られた、本物のモアイ。模アイではない。
防災対策庁舎には、たくさんのお供え物。きっと絶える事なく、放置され朽ち果てる事もなく。
無惨に破壊された気仙沼線の志津川駅は、モダンなデザインのBRT(バス高速輸送システム)の駅として仮復旧。
歌津地区の伊里前商店街ではたくさんのフラッグがはためいている。
大漁旗等でなく何故Jリーグか分からんが、クラブやサポーターから復興を願って寄贈されたものだそうで、そういった意味では本物である。
気仙沼の駅は市街地の外れにある。周辺にこれといった被害は見当たらない。
港に向かって、直角カーブを右に曲がった途端、景色が一変する。
スカスカと不自然に空いた更地。残った建物も、一階部分は軒並み大破している。
市内の3つの仮設商店街と観光協会が、連携してイベントを盛り上げている。大盛況であった。
鹿折地区では、最近まで大きな漁船が打ち上げられて鎮座していた。遺構として残したり公園化する案もあったそうだが、結局撤去されている。
今は嵩上げ事業が活発で、ダンプカーが列をなし、道路の横断もままならないほど。
いくら津波だって、陸地を駆け上がるうちに徐々に減衰し、いつかは止まる。その境目はまるで天国と地獄だ。
市街地外れの丘を昇った辺りは何でもない。普通の田舎道。
建物が密集しアーケード街であったであろう市街地中心部は、全てが流され何も無くなって、まるで箱庭の様である。
高田松原では、流された松の代わりに、山を切り崩した土砂を運ぶベルトコンベアが空中を走る。嵩上げしなければならないから、はるか頭上を走る。
有名な奇跡の一本松は、被災前の7万本の松原の中でも、ひと際大きい一本だったらしい。
三陸鉄道の盛駅は大盛況だ。待合室は混雑で入れないほど。今日も元気に「釜石」行きが出発して行った。
JR大船渡線は、被災した線路を剥がし舗装して、BRT(バス)で仮復旧。可能な限り専用道を走り、渋滞がないので快適である。
当然ながら、被災後に一から構想し整備した訳で、よくぞここまでと思う。本数が多いので、汽車より便利かもしれない。
市内の盛町は官公庁や交通の中心地。大船渡湾からやや奥まった位置にあり、比較的軽微な被害に思えた(それでも浸水はしたらしい)。
商業・経済の中心である隣の大船渡町は湾直近であり、もう根こそぎ。それでもいくつかの商店街が立ち上がり、営業中だ。
一見ガランとしているが、日用品を扱う店舗が多いため。飲食店はそれなりに賑わっている。
更地に下水道のパイプが1m位の高さでにょきにょき立っている。将来そこが地面になるのだろう。